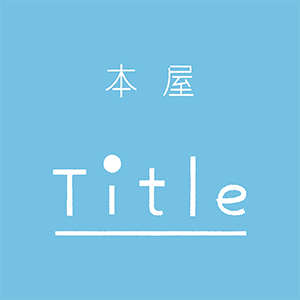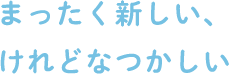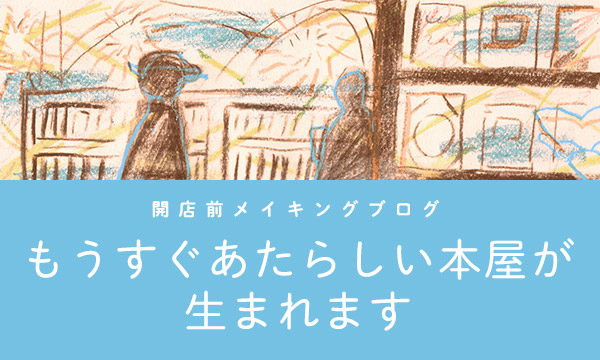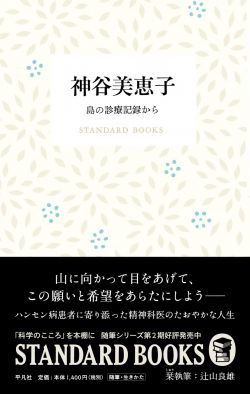 神谷美恵子といえば、ハンセン病療養所での勤務体験をもとに書かれた文章が有名ですが、このシリーズでは、それ以外の家族や恩師について触れた魅力的な文章も多数収録されております。ぜひ、お手に取ってお読みください。
神谷美恵子といえば、ハンセン病療養所での勤務体験をもとに書かれた文章が有名ですが、このシリーズでは、それ以外の家族や恩師について触れた魅力的な文章も多数収録されております。ぜひ、お手に取ってお読みください。
NEWS
執筆の仕事
『読書人 7月21日号 上半期の収穫から』 44人の学者や評論家に聞いた、2017年上半期の収穫と言える本のアンケートです。私が選んだのは、下記の3冊です。
・三品輝起『すべての雑貨』(夏葉社)
・國分功一郎『中動態の世界』(医学書院)
・上間陽子『裸足で逃げる』(太田出版)
大きな書店などで販売している書評紙です。評の文章は、ぜひ現物をご覧ください。
 7月7日発売の雑誌『文藝 2017年秋期号』(河出書房新社)に、書評を寄稿しました。古川日出男さんの、方向性のまったく異なる二冊の新刊『平家物語 犬王の巻』『非常出口の音楽 (7月24日頃発売予定)』(共に河出書房新社)を併せて書くという難しいお題でした。
7月7日発売の雑誌『文藝 2017年秋期号』(河出書房新社)に、書評を寄稿しました。古川日出男さんの、方向性のまったく異なる二冊の新刊『平家物語 犬王の巻』『非常出口の音楽 (7月24日頃発売予定)』(共に河出書房新社)を併せて書くという難しいお題でした。
『犬王の巻』は、古川さんが昨年現代語訳した大著『平家物語』のスピンオフとも言える作品。『非常出口の音楽』は、生が回復する場所に連れていってくれそうな掌篇集です。どちらも面白い本ですので、ぜひご一読ください。
WEBでもお読みいただけます→ http://web.kawade.co.jp/bungei/1583/
共同通信社配信の読書エッセイ「本の森」で、 須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』(白水社)について書いた文章を寄稿しました。「何か心に残る一冊をご紹介ください」というリクエストでしたので、Titleを開店する際に、頭にあった書店のことを書きました。
全国の地方紙の学芸面、読書面に順次掲載されます。お見かけしましたら、ご一読ください。
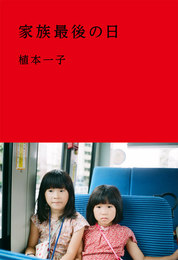 植本一子『家族最後の日』(太田出版)の書評を、北海道新聞書評面(5月7日朝刊)にご掲載いただきました。
植本一子『家族最後の日』(太田出版)の書評を、北海道新聞書評面(5月7日朝刊)にご掲載いただきました。
どうしんウェブからも読むことが可能です。http://dd.hokkaido-np.co.jp/cont/books/2-0113315.html?page=2017-05-07
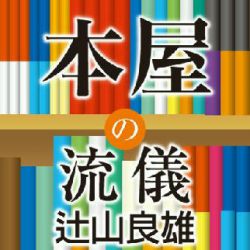 3月28日(火)から、毎週火曜日の『読売新聞 夕刊』に「本屋の流儀」と題したエッセイが、4週に渡り掲載されます。お見かけした際には、ぜひご一読くださいませ。
3月28日(火)から、毎週火曜日の『読売新聞 夕刊』に「本屋の流儀」と題したエッセイが、4週に渡り掲載されます。お見かけした際には、ぜひご一読くださいませ。
 『新潮』4月号に「Titleのある町」というエッセイを書きました。井伏鱒二の『荻窪風土記』が書かれた頃より、この町は本とは縁があるような…そんなことを書いております。ぜひ、ご一読ください。
『新潮』4月号に「Titleのある町」というエッセイを書きました。井伏鱒二の『荻窪風土記』が書かれた頃より、この町は本とは縁があるような…そんなことを書いております。ぜひ、ご一読ください。
なお、この号は又吉直樹さんの『火花』に続く小説第二作目「劇場」が掲載され、4万部発行とのことです。書店の店頭には、数多く並んでいると思います。
 筑摩書房のPR誌『ちくま』の2月号に、稲泉連『「本をつくる」という仕事』の書評を寄稿いたしました。一冊の本が出来上がるまでにかけられる、よき仕事の数々を取材した本です。稲泉さんは『復興の書店』(小学館文庫)という著書もあり、これもまた丁寧に取材された良い本です。書評とあわせてぜひご覧ください。
筑摩書房のPR誌『ちくま』の2月号に、稲泉連『「本をつくる」という仕事』の書評を寄稿いたしました。一冊の本が出来上がるまでにかけられる、よき仕事の数々を取材した本です。稲泉さんは『復興の書店』(小学館文庫)という著書もあり、これもまた丁寧に取材された良い本です。書評とあわせてぜひご覧ください。
なおTitleで『「本をつくる」という仕事』をご購入の方には、ゲラ刷りフリーペーパーと、この『ちくま』2月号を差し上げております。Title購入特典は在庫がなくなり次第終了いたします。https://title-books.stores.jp/items/588c817d100315316d00f528
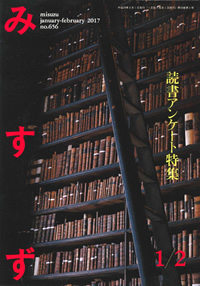 『みすず』1・2月合併号は、恒例の読書アンケート特集です。2016年に出た本の中から5冊を選んで寄稿させて頂きました。
『みすず』1・2月合併号は、恒例の読書アンケート特集です。2016年に出た本の中から5冊を選んで寄稿させて頂きました。
1 細馬宏通 『介護するからだ』 医学書院
2 アン・ウォームズリー 向井和美・訳 『プリズン・ブック・クラブ』 紀伊國屋書店
3 メイ・サートン 幾島幸子・訳 『70歳の日記』 みすず書房
4 天使の聖母 トラピスチヌ修道院 『天使園 「祈り、働け」の日々』 亜紀書房
5 『串田孫一 緑の色鉛筆』 平凡社
それぞれの本の評に関しては、本誌をご覧ください。
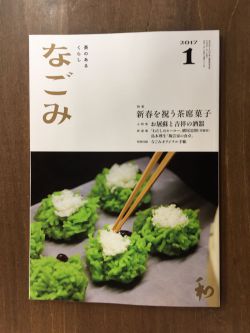 「茶のあるくらし」「グラフィック茶道」とサブタイトルのついた茶道雑誌、『なごみ』での書評の連載が1月号より始まります。広義の日本文化に関する本を選び、文章を寄せております。
「茶のあるくらし」「グラフィック茶道」とサブタイトルのついた茶道雑誌、『なごみ』での書評の連載が1月号より始まります。広義の日本文化に関する本を選び、文章を寄せております。
なお連載は隔月で、誠光社の堀部篤史さんと交代で行う予定です。
『なごみ』は1月号よりリニューアルし、茶道のことだけでなくうつわ、和菓子などその周辺のことに深く触れていたり、宮沢章夫さんやルー大柴さんの連載があったりと、思った以上に若々しい印象の雑誌になっております。お見かけした際は、ぜひ手に取ってみてください。